
2001年〜2002年釜ヶ崎越冬

釜ヶ崎の越冬
毎年、年末年始は「越冬闘争期間」とされています。1970〜1971年の「仲間による仲間の為の越年対策」として始まり、以後毎年継続されています。今回は、2001年12月25日〜2002年1月11日の18日間、第32回目です。主催は、第32回釜ヶ崎越冬闘争実行委員会(釜ヶ崎反失業連絡会等、支援団体7団体による)。
釜ヶ崎は年末年始に仕事がなくなることから、日雇労働者の悲惨や困窮が正月を軸にして集中して表面化します。その上に冬の寒さが覆いかぶさります。そこでこの時期に、労働者たち自身も参加できる形で共に助け合い、そして、野垂れ死にから身を守る闘いを通して、釜ヶ崎における棄民・使い捨て・排除・抹殺の差別構造総体を変革していく質を獲得することを、70年前半の越冬闘争は目的として掲げていました。
「野垂れ死にを許すな」をスローガンに― 12月19日に、越冬闘争支援連帯集会が芦原橋総合福祉センター(大阪市浪速区)で開かれました。基調提案がなされ、「野垂れ死にを許すな!『野宿生活者支援法』の早期成立実現を勝ち取ろう! 反失業闘争を戦いぬいて仕事と住まいを勝ち取ろう!」等のスローガンが確認されました。そして、12月25日に越冬闘争突入集会が三角公園で開かれ、この日より越冬闘争に入りました。
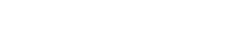 臨時宿泊所
大阪市は、今冬も、「年末年始に仕事が得られないため、自ら食及び住を求めがたい」人への越年対策として住之江区南港に臨時宿泊所(通称:臨泊)を建設し、大阪市立更生相談所で入所受付を行いました。利用期間は12月29日〜1月7日で定員2,800人。今年の利用者数は2,256人(昨年2,217人)で、受付時に飲酒により面接不可能な場合以外は入所が受け入れられました。また、臨泊に先駆けて、12月に入ってから実施された夜間巡回によって施設入所となった人は130人(昨年158人)でした。
臨時宿泊所
大阪市は、今冬も、「年末年始に仕事が得られないため、自ら食及び住を求めがたい」人への越年対策として住之江区南港に臨時宿泊所(通称:臨泊)を建設し、大阪市立更生相談所で入所受付を行いました。利用期間は12月29日〜1月7日で定員2,800人。今年の利用者数は2,256人(昨年2,217人)で、受付時に飲酒により面接不可能な場合以外は入所が受け入れられました。また、臨泊に先駆けて、12月に入ってから実施された夜間巡回によって施設入所となった人は130人(昨年158人)でした。
臨泊では、3食提供され、また、風呂、洗面・洗濯場、テレビ、娯楽室等もあります。利用者はテレビを見たり、仲間と歓談したり囲碁をしたりと思い思いに過ごせますが、臨泊に入らず釜ヶ崎に残る労働者も多い。「荷物があって動けない」、「わしには(臨泊は)窮屈でな」、「南港に行くより釜ヶ崎の方が(正月は)おもしろい」など。
 布団敷き
そんな訳で、臨泊に行かず、釜ヶ崎で踏んばり年を越す労働者のために、毎晩7時半から翌朝5時まで、医療センターの前で布団が敷かれ、労働者に寝場所が提供されました。期間中、1日大体30〜80人の労働者がここを寝場所にしていました。
布団敷き
そんな訳で、臨泊に行かず、釜ヶ崎で踏んばり年を越す労働者のために、毎晩7時半から翌朝5時まで、医療センターの前で布団が敷かれ、労働者に寝場所が提供されました。期間中、1日大体30〜80人の労働者がここを寝場所にしていました。
炊き出し 12月29日から1月3日までは、三角公園が拠点となります。公園 内には大きめのたき火が設営され、それぞれのたき火を20〜30人の労働者が囲み、期間中は毎日、丼や粕汁、雑炊などの炊き出しが行われました。31〜4日は毎食出されました。大晦日には年越しそばが出されました。
内には大きめのたき火が設営され、それぞれのたき火を20〜30人の労働者が囲み、期間中は毎日、丼や粕汁、雑炊などの炊き出しが行われました。31〜4日は毎食出されました。大晦日には年越しそばが出されました。
越冬まつり 31〜3日の4日間、三角公園で越冬まつりが開催されました。のど自慢大会、卓球大会、餅つき大会、ソフトボール大会等の催しがあり、また、連日夕方4時頃から音楽イベントが開催されました。31日には、毎年夏と冬に三角公園で歌っている曽野恵子さんが出演、「釜ヶ崎人情」や「岸壁の母」を 歌われ、「また皆さんの顔を見に帰ってきます」との挨拶で終わられました。
歌われ、「また皆さんの顔を見に帰ってきます」との挨拶で終わられました。
コラム 〜支援の目から①〜
炊き出しをやっていた時のこと。ご飯が一杯盛られた丼と箸を手にしたおっちゃんが、そばにいた私の前で大粒の涙をこぼしはじめた。「ありがとう。これで、もう、いつ死んでもええ。ありがとう。ありがとう」と言いながら…。私は「しっかり食べて、温まってな」と言いながら、おっちゃんと一緒に、ぼろぼろ泣いた。今、目の前にこうしている彼の人生を図り知ることはとてもできない。けれど、ここにある彼の存在を、全身全霊を、ありのまま受けとめたい。それしかできない。おっちゃんのことは、一生忘れない。私のほうが、言い尽くせないほどのありがとう、だ。
人民パトロール 29〜3日の連日夜8時頃より、人民パトロールが、労働者の仲間たちと支援者あわせて100名前後で行われました。釜ヶ崎地域内の他、天王寺や日本橋等へと繰り出し、野宿を余儀なくされている労働者に声をかけながら、おにぎりやカイロを手渡して励ましてまわりました。また、野宿生活者の問題を訴える市民ビラも配られました。道頓堀では、6年前、難波の戎橋で野宿をしていた藤本彰男さんが、若者たちの暴行の末、道頓堀川に投げこまれて殺 された事件を皆で振り返り、藤本氏を追悼して献花を行いました。さらに、天王寺では、2年前に野宿をしていた小林俊春さんが若者たちに襲撃され殺されており、一同で黙祷を捧げました。

府庁デモ 4日は大阪府に対するデモ。府庁舎までの2時間半、堺筋の道行く市民や仕事始めの労働者たちに、釜ヶ崎の反失業、越冬の闘いの訴えがされました。そして、府庁前に到着後、特別就労事業の拡大、半就労・半保護の実施、職業訓練の実施等、11項目の要求を掲げた釜ヶ崎反失業連絡会の要求書が読み上げられ、庁舎より出てきた役人に手渡されました。
医療パトロール 毎晩10時頃より、釜ヶ崎の地域内で(3日に1回は釜ヶ崎の北側、日本橋や難波も)「医療パトロール」が行われました。野宿している人に体の調子を確認しながら、カイロやおにぎり、毛布を渡して回りました。風邪を引いている人に薬を渡したり、顔色蒼白で体調が悪い人は、救急車が呼ばれます。この越冬期間中のパトロールにより、3名の「路上死」が確認されています。
越冬闘争期間が終わっても、野宿生活者の避けることのできない過酷な寒さとの闘いは続きます。医療パトロールは、「夜回り」として支援団体により継続されていきます。
今年も全国各地の多くの方から衣類、毛布等のカンパが寄せられました。また、学生などのボランティアの人たちも多く集まり、炊き出しや医療パトロールに参加されました。野宿生活者は釜ヶ崎・寄場固有の課題から、全国的な「ホームレス問題」へと拡大している時代となっています。身近な現場の発見と取り組みを !
コラム〜支援の目から②〜
とても冷え込んだある晩、医療パトロールをしていると、労働者が路上のダンボールの寝床の中で冷たくなり、息絶えていた。彼の最期を悼んで、パトロールの仲間たちで黙祷し、そしてみんなで泣いた。パトロールのリーダーが言っていた。「私たちは、こぼれ落ちる命を救うことはできない。救えないけれど、寄り添うことならできる。彼らと寄り添い、そして彼らからパワーをいっぱいもらっている」と。こぼれ落ちた彼らの命を、私たちは見守る。そして、彼らの最期を、私たちは忘れない。
コラム越冬闘争とは
越冬闘争とは、冬との闘いである。冬にたち現れる無慈悲な〈権力〉との闘いである。この闘いのなかで、労働者は、先立つ死者に出会う。死者をとおして〈ナカマ〉に出会う。『いつも』の釜ヶ崎から越冬闘争の『ただならぬ』釜ヶ崎への展開のなかで、釜ヶ崎の意味と社会が、劇的に逆転される。
越冬闘争の主役は、死者である。ついで、野宿者である。野宿者は、死者に接する。涙。そして飛翔。生か死か。一歩も後へは引けない。不安と自信。絶望と希望。そして祈りと闘い。越冬闘争は、釜ヶ崎労働者の決定である。力である。文化である。
(青木秀男「生者と死者の対話」、日本解放社会学会編『解放社会学研究2』より)